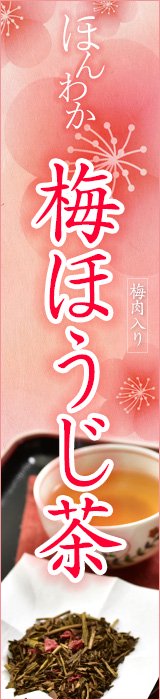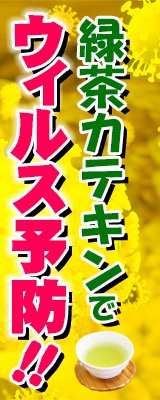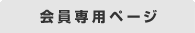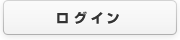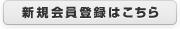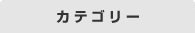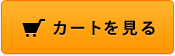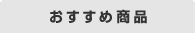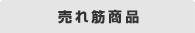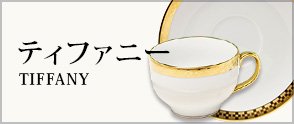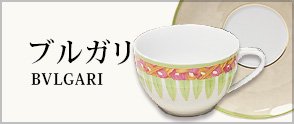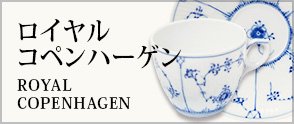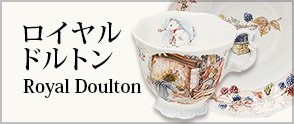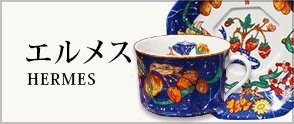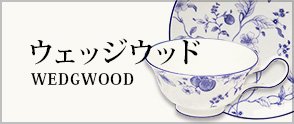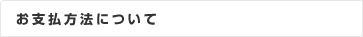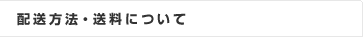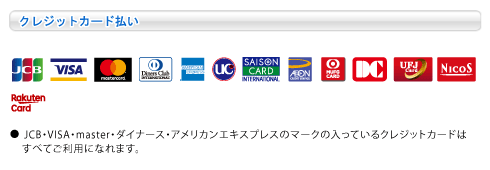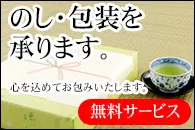
|
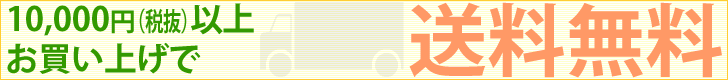 
【送料無料】高岡銅器銅 手付花入
お茶のふじい・藤井茶舗
・合箱付き サイズ: 高さ 28.7cm 幅 19.7cm 重量 1111g 高岡銅器の歴史 高岡銅器の起源は1609年、加賀藩主の前田利長が高岡城へ入城し、高岡の町を開いた際、町の繁栄を図るために、1611年(慶長16年)に礪波郡西部金屋村(現・高岡市戸出西金屋)から、金森弥右衛門ほか7人の鋳造師を現在の高岡市金屋町に呼び寄せたことに始まります。 鋳物師らは御綸旨を代々相伝する、諸役を免除される、関所の通過を自由とするなどといった特権を得ていました。 金屋町に移った当初、鋳物師らは日用の鍋・釜といった鉄器を作っていましたが、後に地域の需要に応える形で銅器生産、多彩な金物生産に移行していきました。 銅器の生産が始まったのは天保・弘化の頃とされています。 明治時代になると廃刀令により職を失った刀職人(御細工人)が銅器産業に参入、日用品から美術工芸品へと変化していきました。 第二次世界大戦中には地金の銅が不足し、代わりにアルミニウムで軍用飛行機部品の生産に転じ、これが富山県における戦後のアルミニウム工業の発展の契機となりました。 1951年(昭和26年)にはアメリカへの輸出用の銅器を生産する業者が現れ、企業間格差が大きくなって行き、1976年(昭和51年)になると高岡鋳物師発祥の地・戸出に高岡銅器団地の建設が始まり、老子製作所などの銅器メーカーが金屋町から銅器団地に移転し始めました。 銅器団地協同組合には現在49社が加盟しており、うち鋳物製造業を営む企業は30社に上ります。  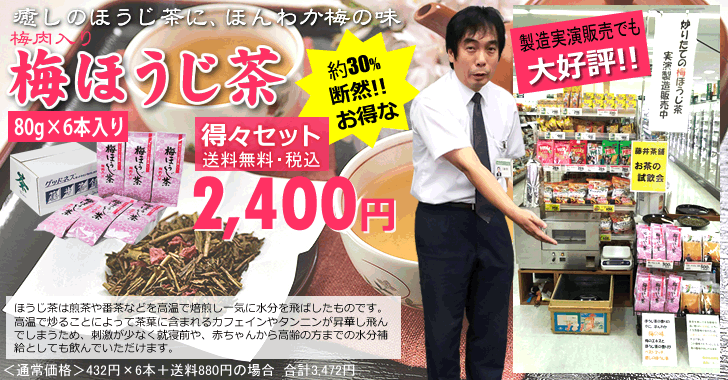


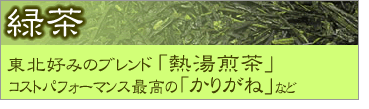  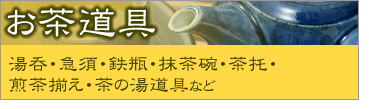 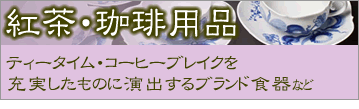
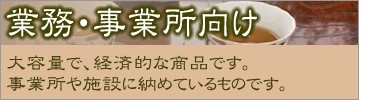 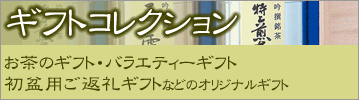

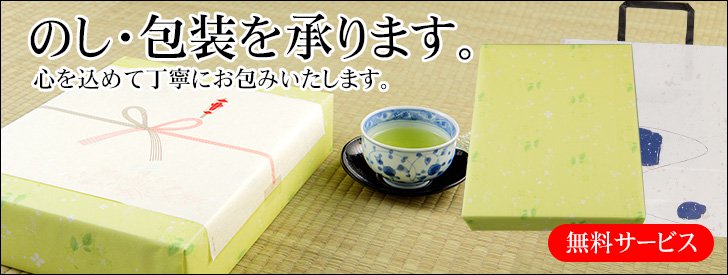 最近チェックした商品
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
創業90余年 湊町酒田のお茶道具・お茶専門店「藤井茶舗」のショッピングサイトです。
|