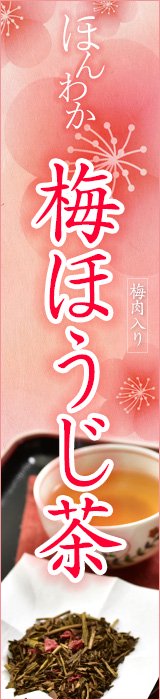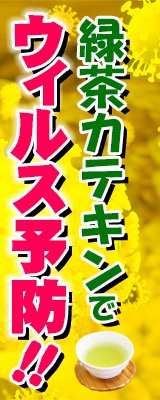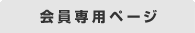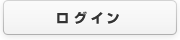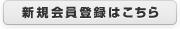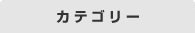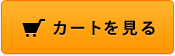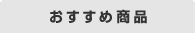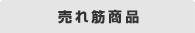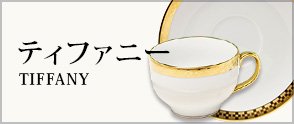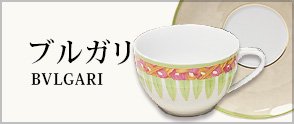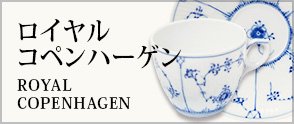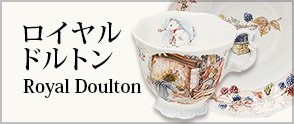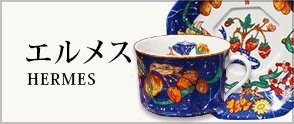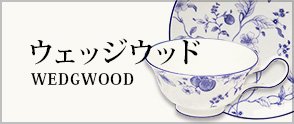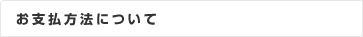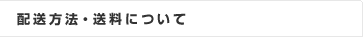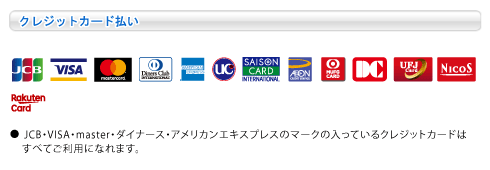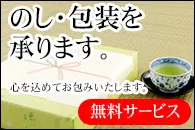
|
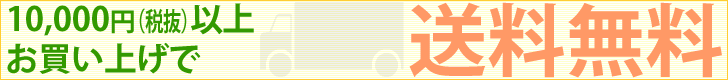 
【送料無料】平清水焼 青龍窯 花入 残雪
お茶のふじい・藤井茶舗
・木箱に少々キズあります サイズ: 口径4.5cm 最大幅 12.3cm 高さ 26cm 平清水焼を今に受け継ぐ山形市の青龍窯 山形市の平清水焼は、諸説あるなかでも江戸末期に始まったと言われています。 最盛期である明治期には、30以上の窯元があったと言われますが、いまもその製法を伝えるのは、2〜3窯のみになってしまいました。そのひとつ、「青龍窯」は、明治初期に創業されました。 初代丈助以来、磁器、陶器などをつくり続けながら、変わりゆく中で、平清水独自のものをつくり出すべく苦心の研究を続けたそうです。そして生まれたのが、「梨青瓷(なしせいじ)」。近くの千歳山の陶石に含まれる鉄分をいかし、梨の肌合いのような青瓷をつくり出しました。そして、さらに現在は艶消しの白釉を施した「残雪」を生み出しました。青や白が透明感あるその美しさは、国内外にファンが多いといいます 山形で最も古い歴史を持ち、文化年間(1804〜1817年)もしくは、それ以前からつくられていたとも伝えられているのが、「平清水焼」です。山形市の東南、千歳山の麓には、いくつかの窯が点在しています。 そのひとつ、明治初期の創業で、平清水焼の開祖の流れをくんでいるのが、青龍窯です。 「残雪」シリーズは、純白の白釉をかけることによって、黒色の斑点が浮き上がることで名づけられました。 やわらかい白の風合いが美しい花入だからこそ、どんなシーンにも映える焼き物です。 平清水焼の歴史 平清水焼は山形市の東南、全山を松の木で覆われた千歳山の南麗に位置する平清水で興りました。 文化年間(1804〜1818年)に同村の人丹羽治左衛門が他の土地から陶工を招き、千歳山の土をもって窯業を行ったのが始まりとされています。 青龍窯の歴史 丹羽治左衛門の流れを汲む青龍窯は、明治初期に丹羽丈助を初代に開窯しました。 時代の変化の中で、磁器・陶器を造りつづける事で、昭和20年千歳山の原土に含まれている鉄分を活かした青瓷を創り出し「梨青瓷」と命名しました。 現在は、四代目丹羽良知がこの伝統を受け継ぎ、今日では梨青瓷のみにとらわれず、「残雪」等を創り自由な釉調と土味を活かした作陶に精進しております。 特色 地元の原土を用い、主に轆轤(ろくろ)成形による手作業によって製造を行っております。 釉薬は山形の雪景色を思わせる白色の《残雪》と、原土の鉄分を活かし梨地の様な風合いに仕上げた《梨青瓷》を特徴としております。  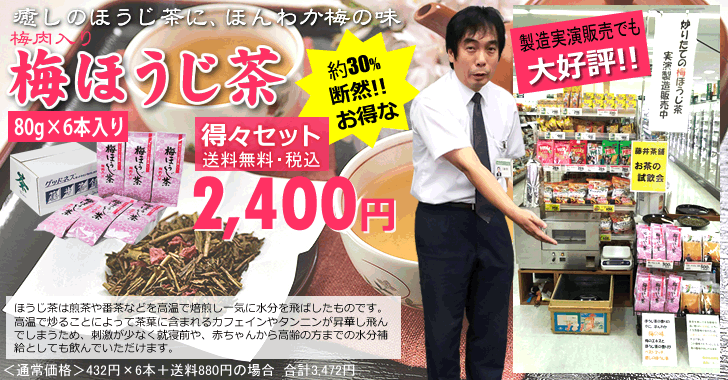


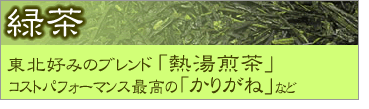  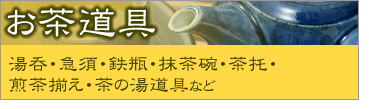 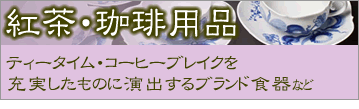
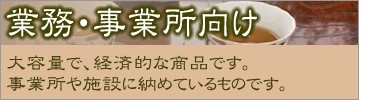 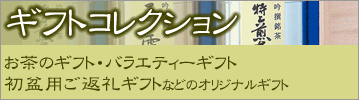

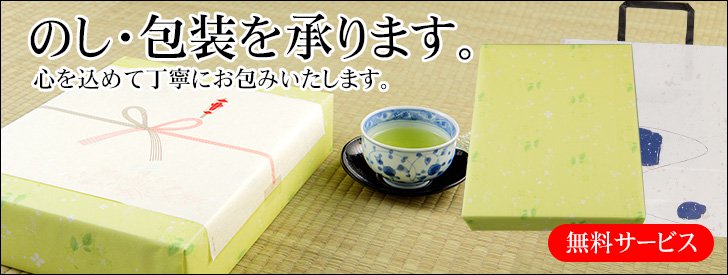 最近チェックした商品
96,000円(税込105,600円) SOLD OUT
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
創業90余年 湊町酒田のお茶道具・お茶専門店「藤井茶舗」のショッピングサイトです。
|